のこぎり屋根のまち
がっしゃん、がっしゃん
朝はやくから、正太のまちではのこぎり屋根の工場からににぎやかな音が響く。
まちでいちばん盛んな産業は、木綿の機織りだった。
まちの至る所に機織り工場があった。
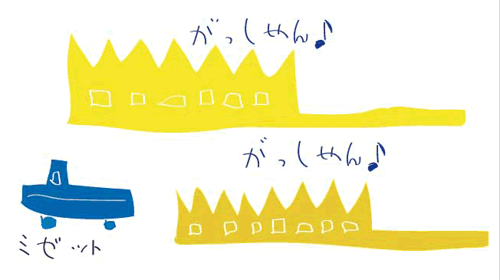
小学校の裏山にのぼると、低い家並みに向こうに、のこぎり型の屋根が海の波のようにつながっているのが見える。
のこぎり屋根のギザギザした一方はすべて南向きで、そこにはガラスがはめられている。一日中南から太陽の光が入るようにするためで、工場はお天道様が昇り始める動きだし、沈むまでがっしゃん、がっしゃんと続いていた。
日の長い夏場は、朝早くから競うように機織り機の音が鳴り始める。
織りあがった布は、主にふとんなど夜具の生地として使われていたが、質がよいと評判で、まちは大いに栄えていた。
夜具には、中に入れる綿が必要で、正太の家の近くには綿を詰める工場もあった。
工場は大願寺の南側の土手の下にあり、大きなマスクをした男たちが広い台の上に綿をのばし布団に詰めている。
正太は窓越しにその作業をみるのが好きだった。
長い篠の棒で綿をたたきながら、整えていく、工場のなかは叩いた綿が舞い上がり、霞がかかったようになっている。ここでは、古くなった綿を打ち直してくれる作業もしていたので、正太の家でも敷き布団の綿の打ち直しを頼んでいた。
「布団の綿は打ち直せば何度でも使えるし、新しく買うよりもやすいし、その上打ち直すとふとんはふかふかしてとてもあたたかいでしょう」
打ち直した布団が届くと、母親はふかふかとした布団を軽く押さえながら、いつもうれしそうにいったものだ。
正太の小学校の同級生の親たちの多くは機織りや布団づくりの仕事に関わっていた。
ある親は工場の経営者であり、ある親は織り機を操作する仕事をしており、ある親は工場の事務、ある親は織り終わった布を運ぶトラックの運転手、そしてある親は織物組合につとめている。
正太の家のように、まちでは珍しいサラリーマン家庭とはちがって、工場で働く家庭では、いつも親たちが身近にいる。
夕方になると仕事帰りの親と手をつなぎ楽しそうに家路につく同級生の姿をよく見かけた。
「どうしてお父さんは、いつも夜遅くにしか帰ってこないの?」と母親に話してみても、返ってくる答えはいつも同じだった。
「お父さんが勤める会社は、日本橋にあるから仕事が終わってから帰るまで1時間以上かかるのでしかたないでしょう」
「なんでこのまちに勤めないのかな、そうすればみんなと同じように、ボクもお父さんを迎えに行けるのに」
「そうね、戦争がなかったら疎開することもなかったし、空襲で家が焼かれることもなかったから、お父さんの勤める会社も近くて、早く家に帰ってこられるかもしれないけれど、いまは仕方ないでしょう」
戦争や疎開は、正太の記憶にはまったくないことだが、母親の話ではつい昨日あったことのように思える。
「お母さん、僕たちはもう昔住んでいたところに帰れないの」
「さあ、どうかしら。それはわからない」
「僕は、友達もいっぱいいるからこのまちが好きだよ」
「そうね、お母さんもいいまちだと思う」
「お姉ちゃんや、お兄ちゃんがどう思ってるのかな」
「それは正太が聞いてみればいいでしょう」
「お父さんが、このまちに勤めていればもっといいのになあ」
正太の思いは、いつもそこにあった。
秋子の家
秋子の家は、大きな織物工場を営んでいた。
初めてその家を訪ねたのは小学校1年生の秋の終わり頃だった。
母親が小学校のPTAのことで、秋子の家にいく用事があり正太を一人で留守番させるのは心配だからと、いっしょにいくことになった。
家をでて大願寺の山門前の坂を下り、踏切をこえる。
大願寺の坂を下るときに、八百屋や豆腐屋のおばさんが一言二言声をかけてくる。
「正チャンきょうはお母さんといっしょでいいね」と豆腐屋のおばさん。
色白で太っていて、目が細いので正太は「お母さん、豆腐屋のおばさんは目が見えているのかな」ときいてひどくしかられたことがある。
今日もやっぱり目が見えているのかどうか、わからないほど細い目で正太の方をみていた。
そんな豆腐屋のおばさんが正太は好きだった。
小さな鍋をもって豆腐を買いにいくと必ずお駄賃にお菓子などくれる。
お菓子がないと、「油揚げいちまいおまけしておくからね」と威勢のいい声で、新聞紙にくるんだ油揚げを鍋のふたの上にのせてくれた。
買ったばかりの豆腐をもって、夕方の暗い坂道を上って帰ると、店先に座っている八百屋のおばさんが「おつかいかい、えらいね。気をつけてお帰り」と声をかけくる。
八百屋のおばさんは「マンさん」と呼ばれていた。
八百屋のマンさんも、おつかいで野菜などを買いに行くと、おまけにリンゴやみかんをくれることがあった。
そして、お釣りを渡すときに特に大きな声で「はい、きゅうり一本8万円、10万円のあずかりで2万円のおつり」ときまってお釣りに万円をつけた。
だからマンさんと呼ばれているのだなと、正太は勝手に合点していた。でもある時、ふと八百屋の店の柱にうち付けられている表札を見たら、そこにお店のおじさんの名前と並んでひらがなで「まん」と書かれてあった。
正太の母親は、声をかけてくる店のおばさんたちに頭を下げながら「いつも正太がお世話になっています」と言葉を返している。
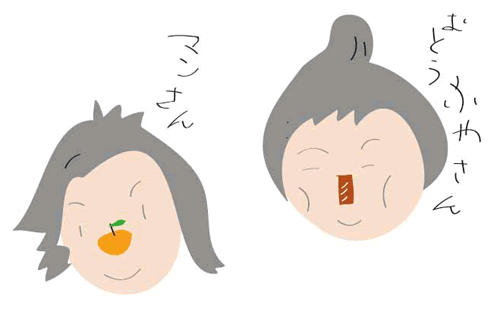
坂下の踏切をわたると左側にそそり立つように、祭りの山車小屋が建っており、その前は子どもが遊ぶ広場になっていて、町内の顔見知りが「おう、しょうた」とか、「おっかあとでかけるのか」とか、遊びの手を止めて声をかけてくる。
質屋の黒塀にそって右に曲がり、まっすぐの道をさらに歩く。
母親の足の運びが早くなる。
「正太、せっせと歩きなさい」
遅れ気味の正太に、母親は振り向くこともなく声をかける。
道路の左右は家並みが途切れて、畑地になっている。
「お母さん、畑に野菜がいっぱいだよ」
「正太、なんのお野菜かわかる?」
「大根でしょう。それから、キャベツもある」
「あれは白菜」
「白菜?」
「正太は、白菜の漬け物がすきでしょう」
「うん、すきだよ」
「これから、寒くなっていくと白菜はおいしくなるの」
「まだ、遠いいの?おかあさん」
「そうね、もう少しいって左に曲がると大きな坂があるでしょう。坂を下ったらすぐよ」
その坂は、夏に子どもたちの川遊びの場所になっている釜の淵につながる。
正太はまだ小さいので、父親や母親に一度か二度連れていかれただけで、夏以外の季節に坂を下るのは初めてだった。
街道をわたると坂上にでる。そこから川向こうに景色が広がっている
遠くの山は、紅葉が始まって紅く染まっている。
坂はごつごつとして石ころが転がっていて歩きにくい。
「走ったりすると転ぶから気をつけなさい」
母親の言葉を背中で聞きながら、それでも広い坂道をちょっと小走りに下る。
ちょうどそのとき、坂の下からバスがうんうん唸りながらあがってきた。
「正太バスですよ、道路脇によりなさい」
坂道の途中でバスは苦しそうにあえぎながら速度を落とした。バスの後ろ側から煙突が飛び出ており、黒い煙が立ち上っている。
「お母さんバスが苦しそうだよ」
「あらあら、バスさんが息切れしたようね」
バスは完全に止まってしまった。
すると、バスの扉が開き、女車掌が降りてきて、後ろに回ると煙突のついている銀色の釜のふたをあけて、そばに積んであった薪をくべ始めた。
しばらくすると黒い煙が白くなり、バスは息を吹き返したものの、それでも苦しげに坂を上り始める。
正太は乗り物ならなんでも好きだった。電車が一番でその次がバスだった。飛行機も好きなのだがおもちゃと絵本の世界だけで本物を見たことがない。船は戦争中の絵本にある軍艦しか知らない。
「お母さん、あのバスはウチのお風呂みたいにお釜で木を燃やしていたよ?」
「あれは木炭バスといって、蒸気機関車のように木を燃やして蒸気を湧かして走るのよ」
バスを見送って、少し歩くと右に上り道があり、母親が手を引いてそちらに向かう。
秋子の家は道を曲がってしばらくすると見えてきた。
秋子はシュウコ
最初に目に飛び込んできたのは、何棟もあるのこぎり屋根の工場だった。そこからはがっしゃんがっしゃんという音が聞こえてくる。
正太の母親は、のこぎり屋根の工場の手前にある二階建ての家の玄関の引き戸を開き、ごめんくださいと声をかけながら入っていく。
正太も後に続いたが、中は土間になっていて暗かった。目が慣れると、土間の先は、板の間になっていて人がせわしく働いていた。
母親が名前をつげると、一人が奥に入って少しすると、正太の母親と同じくらいの和服姿の女性がにこにこしながら出てきた。
「まあまあ、ご足労いただいて申し訳ありません」女性は頭にかぶってた手ぬぐいをとりながら板の間にすわり丁寧に頭を下げる。
「いえいえ、お忙しい時間におじゃましてもうしわけありません」と、母親は腰を低くして頭を下げる。正太もぺこりと頭をさげた。
「ちゃんとごあいさつなさい」
母親に促されて、挨拶しようと思ったら、「正太君でしょう、シュウコがいつもおせわになって、ありがとうございます。正太君はとてもやさしいって、小学校から帰るといつもいってます」
どうぞお上がりくださいと、いわれ母親について土間から板の間にあがった。母親を真似て振り向いて脱いだ靴をそろえる。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、と働いている人たちから声がかかる。
母親は、その声にいちいち頭を下げながら、奥に進んでいく。
正太は訳もわからないまま後についていく。
やがて、広い庭に面した二間続きの和室につく。
手前の和室には、どっしりした黒い座卓が真ん中に置かれ、ふすまが開け放たれた隣の和室には、金色に輝く天井までとどくような仏壇があった。
「いまシュウコをよんできましょう」
そういって秋子の母親が席をはずす。
「お母さんシュウコって誰のこと」
「正太は知らなかったの、みんなアキコちゃんてよんでいるけれど、本当はシュウコちゃんていうの」
「だって、先生だってアキコちゃんってよんでいるよ」
そこへ、足音が聞こえ、秋子をつれて母親が帰ってきた。
「正太君のおかあさん、こんにちは」
秋子はちょこんと正座すると、丁寧に頭を下げた。
「あらあらシュウコちゃん、上手にご挨拶できたこと」
「正太さん、シュウコといっしょに工場の方で、遊んでいらっしゃいな。これから、お母さんとお話しがありますから」
「正太、お仕事のじゃまにならないように気をつけて。シュウコちゃんよろしくおねがいします」
「はい、正太君いっしょにいきましょう」
正太は、学校で勉強しているときよりもずっと大人びて見える秋子にちょっと気後れしてついていった。
「正太君、機織り工場見るの、はじめて?」
「うん、ちょっとのぞいたことはあるけれど」
「こっちにきて」
手招きして、秋子はずんずんと家の奥に進んでいく。廊下をいくつも曲がっていくと次第にがっしゃん、がっしゃんという音が大きくなってきた。
「秋子ちゃんの家って大きいうちだね。迷子にならない」
「自分のうちだもの、迷子になったら困るでしょ」
前をいく秋子の髪の毛は先の方が縮れていて、くるっと外に巻いている。小学校でパーマネントかけているみたいといわれ、これは生まれつきよ、と秋子は答えていた。
「テンパーか」誰かが大きな声でいった。
「テンパー」「テンパー」男の子がはやし立てる。
正太はテンパーの意味がわからないので、黙ってみていた。
朝はやくから、正太のまちではのこぎり屋根の工場からににぎやかな音が響く。
まちでいちばん盛んな産業は、木綿の機織りだった。
まちの至る所に機織り工場があった。
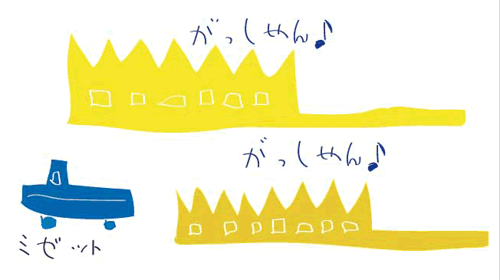
小学校の裏山にのぼると、低い家並みに向こうに、のこぎり型の屋根が海の波のようにつながっているのが見える。
のこぎり屋根のギザギザした一方はすべて南向きで、そこにはガラスがはめられている。一日中南から太陽の光が入るようにするためで、工場はお天道様が昇り始める動きだし、沈むまでがっしゃん、がっしゃんと続いていた。
日の長い夏場は、朝早くから競うように機織り機の音が鳴り始める。
織りあがった布は、主にふとんなど夜具の生地として使われていたが、質がよいと評判で、まちは大いに栄えていた。
夜具には、中に入れる綿が必要で、正太の家の近くには綿を詰める工場もあった。
工場は大願寺の南側の土手の下にあり、大きなマスクをした男たちが広い台の上に綿をのばし布団に詰めている。
正太は窓越しにその作業をみるのが好きだった。
長い篠の棒で綿をたたきながら、整えていく、工場のなかは叩いた綿が舞い上がり、霞がかかったようになっている。ここでは、古くなった綿を打ち直してくれる作業もしていたので、正太の家でも敷き布団の綿の打ち直しを頼んでいた。
「布団の綿は打ち直せば何度でも使えるし、新しく買うよりもやすいし、その上打ち直すとふとんはふかふかしてとてもあたたかいでしょう」
打ち直した布団が届くと、母親はふかふかとした布団を軽く押さえながら、いつもうれしそうにいったものだ。
正太の小学校の同級生の親たちの多くは機織りや布団づくりの仕事に関わっていた。
ある親は工場の経営者であり、ある親は織り機を操作する仕事をしており、ある親は工場の事務、ある親は織り終わった布を運ぶトラックの運転手、そしてある親は織物組合につとめている。
正太の家のように、まちでは珍しいサラリーマン家庭とはちがって、工場で働く家庭では、いつも親たちが身近にいる。
夕方になると仕事帰りの親と手をつなぎ楽しそうに家路につく同級生の姿をよく見かけた。
「どうしてお父さんは、いつも夜遅くにしか帰ってこないの?」と母親に話してみても、返ってくる答えはいつも同じだった。
「お父さんが勤める会社は、日本橋にあるから仕事が終わってから帰るまで1時間以上かかるのでしかたないでしょう」
「なんでこのまちに勤めないのかな、そうすればみんなと同じように、ボクもお父さんを迎えに行けるのに」
「そうね、戦争がなかったら疎開することもなかったし、空襲で家が焼かれることもなかったから、お父さんの勤める会社も近くて、早く家に帰ってこられるかもしれないけれど、いまは仕方ないでしょう」
戦争や疎開は、正太の記憶にはまったくないことだが、母親の話ではつい昨日あったことのように思える。
「お母さん、僕たちはもう昔住んでいたところに帰れないの」
「さあ、どうかしら。それはわからない」
「僕は、友達もいっぱいいるからこのまちが好きだよ」
「そうね、お母さんもいいまちだと思う」
「お姉ちゃんや、お兄ちゃんがどう思ってるのかな」
「それは正太が聞いてみればいいでしょう」
「お父さんが、このまちに勤めていればもっといいのになあ」
正太の思いは、いつもそこにあった。
秋子の家
秋子の家は、大きな織物工場を営んでいた。
初めてその家を訪ねたのは小学校1年生の秋の終わり頃だった。
母親が小学校のPTAのことで、秋子の家にいく用事があり正太を一人で留守番させるのは心配だからと、いっしょにいくことになった。
家をでて大願寺の山門前の坂を下り、踏切をこえる。
大願寺の坂を下るときに、八百屋や豆腐屋のおばさんが一言二言声をかけてくる。
「正チャンきょうはお母さんといっしょでいいね」と豆腐屋のおばさん。
色白で太っていて、目が細いので正太は「お母さん、豆腐屋のおばさんは目が見えているのかな」ときいてひどくしかられたことがある。
今日もやっぱり目が見えているのかどうか、わからないほど細い目で正太の方をみていた。
そんな豆腐屋のおばさんが正太は好きだった。
小さな鍋をもって豆腐を買いにいくと必ずお駄賃にお菓子などくれる。
お菓子がないと、「油揚げいちまいおまけしておくからね」と威勢のいい声で、新聞紙にくるんだ油揚げを鍋のふたの上にのせてくれた。
買ったばかりの豆腐をもって、夕方の暗い坂道を上って帰ると、店先に座っている八百屋のおばさんが「おつかいかい、えらいね。気をつけてお帰り」と声をかけくる。
八百屋のおばさんは「マンさん」と呼ばれていた。
八百屋のマンさんも、おつかいで野菜などを買いに行くと、おまけにリンゴやみかんをくれることがあった。
そして、お釣りを渡すときに特に大きな声で「はい、きゅうり一本8万円、10万円のあずかりで2万円のおつり」ときまってお釣りに万円をつけた。
だからマンさんと呼ばれているのだなと、正太は勝手に合点していた。でもある時、ふと八百屋の店の柱にうち付けられている表札を見たら、そこにお店のおじさんの名前と並んでひらがなで「まん」と書かれてあった。
正太の母親は、声をかけてくる店のおばさんたちに頭を下げながら「いつも正太がお世話になっています」と言葉を返している。
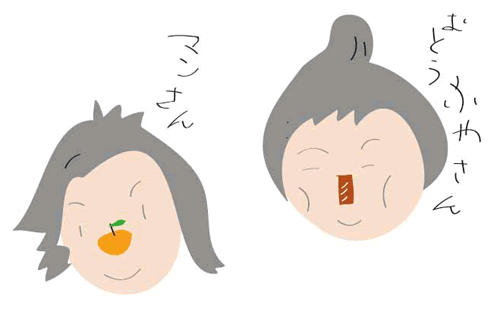
坂下の踏切をわたると左側にそそり立つように、祭りの山車小屋が建っており、その前は子どもが遊ぶ広場になっていて、町内の顔見知りが「おう、しょうた」とか、「おっかあとでかけるのか」とか、遊びの手を止めて声をかけてくる。
質屋の黒塀にそって右に曲がり、まっすぐの道をさらに歩く。
母親の足の運びが早くなる。
「正太、せっせと歩きなさい」
遅れ気味の正太に、母親は振り向くこともなく声をかける。
道路の左右は家並みが途切れて、畑地になっている。
「お母さん、畑に野菜がいっぱいだよ」
「正太、なんのお野菜かわかる?」
「大根でしょう。それから、キャベツもある」
「あれは白菜」
「白菜?」
「正太は、白菜の漬け物がすきでしょう」
「うん、すきだよ」
「これから、寒くなっていくと白菜はおいしくなるの」
「まだ、遠いいの?おかあさん」
「そうね、もう少しいって左に曲がると大きな坂があるでしょう。坂を下ったらすぐよ」
その坂は、夏に子どもたちの川遊びの場所になっている釜の淵につながる。
正太はまだ小さいので、父親や母親に一度か二度連れていかれただけで、夏以外の季節に坂を下るのは初めてだった。
街道をわたると坂上にでる。そこから川向こうに景色が広がっている
遠くの山は、紅葉が始まって紅く染まっている。
坂はごつごつとして石ころが転がっていて歩きにくい。
「走ったりすると転ぶから気をつけなさい」
母親の言葉を背中で聞きながら、それでも広い坂道をちょっと小走りに下る。
ちょうどそのとき、坂の下からバスがうんうん唸りながらあがってきた。
「正太バスですよ、道路脇によりなさい」
坂道の途中でバスは苦しそうにあえぎながら速度を落とした。バスの後ろ側から煙突が飛び出ており、黒い煙が立ち上っている。
「お母さんバスが苦しそうだよ」
「あらあら、バスさんが息切れしたようね」
バスは完全に止まってしまった。
すると、バスの扉が開き、女車掌が降りてきて、後ろに回ると煙突のついている銀色の釜のふたをあけて、そばに積んであった薪をくべ始めた。
しばらくすると黒い煙が白くなり、バスは息を吹き返したものの、それでも苦しげに坂を上り始める。
正太は乗り物ならなんでも好きだった。電車が一番でその次がバスだった。飛行機も好きなのだがおもちゃと絵本の世界だけで本物を見たことがない。船は戦争中の絵本にある軍艦しか知らない。
「お母さん、あのバスはウチのお風呂みたいにお釜で木を燃やしていたよ?」
「あれは木炭バスといって、蒸気機関車のように木を燃やして蒸気を湧かして走るのよ」
バスを見送って、少し歩くと右に上り道があり、母親が手を引いてそちらに向かう。
秋子の家は道を曲がってしばらくすると見えてきた。
秋子はシュウコ
最初に目に飛び込んできたのは、何棟もあるのこぎり屋根の工場だった。そこからはがっしゃんがっしゃんという音が聞こえてくる。
正太の母親は、のこぎり屋根の工場の手前にある二階建ての家の玄関の引き戸を開き、ごめんくださいと声をかけながら入っていく。
正太も後に続いたが、中は土間になっていて暗かった。目が慣れると、土間の先は、板の間になっていて人がせわしく働いていた。
母親が名前をつげると、一人が奥に入って少しすると、正太の母親と同じくらいの和服姿の女性がにこにこしながら出てきた。
「まあまあ、ご足労いただいて申し訳ありません」女性は頭にかぶってた手ぬぐいをとりながら板の間にすわり丁寧に頭を下げる。
「いえいえ、お忙しい時間におじゃましてもうしわけありません」と、母親は腰を低くして頭を下げる。正太もぺこりと頭をさげた。
「ちゃんとごあいさつなさい」
母親に促されて、挨拶しようと思ったら、「正太君でしょう、シュウコがいつもおせわになって、ありがとうございます。正太君はとてもやさしいって、小学校から帰るといつもいってます」
どうぞお上がりくださいと、いわれ母親について土間から板の間にあがった。母親を真似て振り向いて脱いだ靴をそろえる。
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、と働いている人たちから声がかかる。
母親は、その声にいちいち頭を下げながら、奥に進んでいく。
正太は訳もわからないまま後についていく。
やがて、広い庭に面した二間続きの和室につく。
手前の和室には、どっしりした黒い座卓が真ん中に置かれ、ふすまが開け放たれた隣の和室には、金色に輝く天井までとどくような仏壇があった。
「いまシュウコをよんできましょう」
そういって秋子の母親が席をはずす。
「お母さんシュウコって誰のこと」
「正太は知らなかったの、みんなアキコちゃんてよんでいるけれど、本当はシュウコちゃんていうの」
「だって、先生だってアキコちゃんってよんでいるよ」
そこへ、足音が聞こえ、秋子をつれて母親が帰ってきた。
「正太君のおかあさん、こんにちは」
秋子はちょこんと正座すると、丁寧に頭を下げた。
「あらあらシュウコちゃん、上手にご挨拶できたこと」
「正太さん、シュウコといっしょに工場の方で、遊んでいらっしゃいな。これから、お母さんとお話しがありますから」
「正太、お仕事のじゃまにならないように気をつけて。シュウコちゃんよろしくおねがいします」
「はい、正太君いっしょにいきましょう」
正太は、学校で勉強しているときよりもずっと大人びて見える秋子にちょっと気後れしてついていった。
「正太君、機織り工場見るの、はじめて?」
「うん、ちょっとのぞいたことはあるけれど」
「こっちにきて」
手招きして、秋子はずんずんと家の奥に進んでいく。廊下をいくつも曲がっていくと次第にがっしゃん、がっしゃんという音が大きくなってきた。
「秋子ちゃんの家って大きいうちだね。迷子にならない」
「自分のうちだもの、迷子になったら困るでしょ」
前をいく秋子の髪の毛は先の方が縮れていて、くるっと外に巻いている。小学校でパーマネントかけているみたいといわれ、これは生まれつきよ、と秋子は答えていた。
「テンパーか」誰かが大きな声でいった。
「テンパー」「テンパー」男の子がはやし立てる。
正太はテンパーの意味がわからないので、黙ってみていた。
秋子はちょっと猫背で、顎が少し前にでている。笑うと半円型をした目がやさしく、西洋人形のような髪型とよくあっているので、「テンパー」とはやし立てる気持ちになれなかった。
秋子は、はやし立てられてもにこにこ笑っているだけなので、いつの間にか騒いでいた男子もおとなしくなってしまった。
静かで口数が少ない、どちらかというと大人しい秋子を見慣れている正太にとって、目の前のいるのは別の秋子なのではないかと思えるほどはきはきしていた。
ガラスの入った格子戸を開けると、がっしゃん、がっしゃんという音が、まるで吹き出すように響いてきた。
「すごい」正太は音にも驚いたけれど、工場の広さに度肝を抜かれ思わず声をあげたけれど、秋子には全く聞こえていない。
見渡す限り黒光りした機織り機が生き物のように動いている。
規則正しく並んでいる何本もの柱が天井には太い梁を支えている。その梁の所々から電球がぶら下がっている。梁の上の、こぎり屋根のあかり窓から光が差しており、工場の中は明るい。
機織り機の前の床には、すのここがしかれていて、その上で頭に手ぬぐいをかぶった女性達が忙しく働いている。
秋子が機織り機の前で、正太に話しかけているが、よく聞こえない。
無数の糸ががっしゃんと上下に交差するたびに手前に布が伸びてくるのを、秋子が正太に指差しながら話し続けている。布には模様があって、正太はどうして糸が上下するだけで、こんな模様ができるのか不思議でならなかった。
すのこの上を正太と秋子は、工場の奥へと向かう。
機械と機械の間は狭くはないけれど、女性が働いているので邪魔にならないように歩かなければならない。秋子はなれた足取りでずんずんと先にいく。
入ってきたときと反対側の引き戸を開けると、そこが事務所になっていた。
引き戸を閉めると機織り機の音が静かになる。
「お父さん、正太くんが遊びに来たから工場を見せてあげたの」
お父さんと呼ばれた男の人が椅子から立ち上がった。
見上げるほど背が高く、がっしりとした体格だったが、見つめる眼が秋子にそっくりで、やさしくほほえんでいる。
「いらっしゃい」声もやさしい。
「こんにちは」正太はそう言うのが精一杯だった。
「シュウコと仲良くしてくれているそうで、ありがとう」
秋子のお父さんもシュウコといっている。
「正太くん工場どうだった。すごい音だったでしょう」
感想を求められて正太はどう返事を返していいものか、困ってしまった。
こんな広い工場を見たこともなかったし、びっくりするほど機織り機は並んでいるし、その機織り機から魔法のように布ができてくるし。
「そうか、びっくりしてどういっていいかわからないか」
秋子のお父さんは、正太の気持ちがわかったようにさらに目をやさしく細めて、頷いていた。
正太は機織り機が動くのをもっと見ていたいと思っていたが、30分ほどして母親達のいる和室に戻った。
和室の大きな座卓の上には、菓子をのせた鉢が置かれていた。
「正太さん遠慮無く召し上がれ」
秋子の母親にすすめられて正太は、ちょっと自分の母親をみながら、鉢の中から茶色くて平たい菓子を手にとった。秋子も同じ菓子を手に取る。
「お母さんのこのお菓子なんていうの」
「それは三笠焼き。せっかくだからいただきなさい」
三笠焼は、少年雑誌でみた円盤のような形をしている。上下の円盤のなかにあんこが挟まっていて、香ばしい円盤とあんこをいっしょに噛むと、いままで食べたことのない幸せな味がした。
「おいしい」
一気に食べるのがもったいないくらいの甘さだった。
「正太さん、これからもシュウコと仲良くしてくださいね」
口の中に三笠焼をほおばったまま、正太は大きく首をたてにふった。
こんなおいしいお菓子を食べさせてもらったら、誰の頼みだってことわれないと、正太なりに思っていた。
帰り道、正太はなんで秋子はシュウコというのかと母親にたずねた。
「シュウコちゃんの誕生日は、立秋の日だったので秋の子と書いてシュウコという名前にしたそうよ。でもね、小学校に入ってからシュウコちゃんはシュウコという名前が好きじゃないって、どうしてもアキコじゃなくてはいやだといいだしたんですって」
「立秋ってなあに」
「そうね、今日から秋が始まりますよ、という日のこと」
「ふうん、秋子ちゃんは秋になる日に生まれたということか」
正太は、どうしてシュウコではいけないのか、分からなかった。でも、学校と家とで名前が二つあるというのは、ちょっぴり羨ましかった。
お迎え秋子
初めて秋子の家に行った翌日のことだった。小学校へいく準備をしている正太の耳に、玄関のほうから大きな声が聞こえてきた。
「ショウタくん、学校へ行きましょう」
シ・ヨ・ウ・タ・ク・ンと一言ずつ区切るようにしゃべっている。
「正太、誰かがお迎えにきてるから急ぎなさい」
正太は、大あわてでランドセルを背負い、鉛筆箱をカタカタと鳴らしながら玄関に急いだ。
玄関先の石段の下にいたのは、秋子ともうひとり知らない女の子だった。
それがすべての始まりだった。
その日いらい、雨の日も風の日も、雪の日も日曜日と旗日と夏休み、冬休み以外は、毎朝「シ・ヨ・ウ・タ・ク・ン」の声が玄関先から聞こえるようになった。
「ほら、正太、ガールフレンドがお迎えよ」
小さい方の姉が、秋子の声を聞きつけると正太をからかう。
でも、正太はそんなことは気にしなかった。
秋子が迎えに来てくれるのがたのしみでもあった。
確かに声をかけてくるのは秋子だったが、みんなと連れだって小学校に行くことにかわりはないし、ほんの5分ほどの距離をぺちゃくちゃおしゃべりしながら通うのはたのしい時間だった。
二年生になってもお迎え秋子は毎日玄関先で呼びかけてきたが、3年生になってしばらくして、とつぜん終わりになった。
小学生同士の喧嘩のきっかけはささいなことから始まる。
その時もそうだった、正太は、クラスはちがうが同じ町内の友だちたちと遊んでいたときに、いい争いになった。
争いの原因はベーゴマだった。正太はベーゴマが苦手で、その日も大切にしていたベーゴマをはじき出されて取られてしまった。取り返すために挑戦してはまた取られるで、正太はつい、勝てない相手のベーゴマについて「君のベーゴマはお兄ちゃんが削ったやつだからずるい」といってしまったのだ。
八角形のベーゴマの角を削り鋭くすることで、仲間のベーゴマをはじき出すことができる。正太たちは競って、コンクリートの壁や階段などにベーゴマをこすりつけたりして、角を鋭くした。だが、子どもの力ではそんなに削れない。兄弟のいる友だちは年上の兄に助けてもらったり、時には兄たちのベーゴマを持ってくるときもある。
正太が悔し紛れに思わずいってしまった「ずるい」というひとことで、火がついてしまった。
「なんだ正太なんか、女といっしょに学校へ行ってるじゃないか」
秋子といっしょに小学校へ行っていることが"ずるい"ことといわれて正太は言葉に詰まり、小さな声で「そんなのベーゴマと関係ないじゃないか」と言い返すのがやっとだった。
「ほらみろ、正太は秋子と結婚の約束でもしたのか。いつもおててつないで仲良くっていいな」
いっしょに遊んでいた他の仲間も加勢し始め「シ・ヨ・ウ・タ・ク・ン、いっしょの学校へいきましょ」と、秋子の口まねまでしてくる。
「ボクは、秋子なんか別になんでもないよ」
喧嘩のそっちのけで、正太はむきになって言い返す。
「明日、また秋子がむかえにきたらいっしょに学校いくんだろう」
からかうようにはやしたててくる。
「行かないよ、絶対に行かないよ」と強がっていってしまった翌朝から、正太は誰よりも早く起きて小学校へ行くようになった。
「正太、シュウコちゃんが迎えにきたのになんで先に行ってしまったの」
下校してきたときに母親からいわれたが正太は黙っていた。
その翌朝も、そして次の翌朝も正太は、シュウコが迎えにくる前に家を出た。
正太の母親は、シュウコに「正太は、なんだかシュウコちゃんといっしょに学校へ行くのが恥ずかしいみたいで、ごめんなさいね」と、あやまるのがやっとだった。
秋子は、時間を早めて迎えに来ることもあった。
迎えの声を聞くと、正太はランドセルを背負って、家の裏の崖をよじ登って、山伝いに小学校へ向かったりした。
小学校3年生の夏休みが終わり二学期になると、秋子はのお迎えも終わりになった。
だが、正太と秋子の話はまだまだ続く、続きはまたの機会ということに。
秋子は、はやし立てられてもにこにこ笑っているだけなので、いつの間にか騒いでいた男子もおとなしくなってしまった。
静かで口数が少ない、どちらかというと大人しい秋子を見慣れている正太にとって、目の前のいるのは別の秋子なのではないかと思えるほどはきはきしていた。
ガラスの入った格子戸を開けると、がっしゃん、がっしゃんという音が、まるで吹き出すように響いてきた。
「すごい」正太は音にも驚いたけれど、工場の広さに度肝を抜かれ思わず声をあげたけれど、秋子には全く聞こえていない。
見渡す限り黒光りした機織り機が生き物のように動いている。
規則正しく並んでいる何本もの柱が天井には太い梁を支えている。その梁の所々から電球がぶら下がっている。梁の上の、こぎり屋根のあかり窓から光が差しており、工場の中は明るい。
機織り機の前の床には、すのここがしかれていて、その上で頭に手ぬぐいをかぶった女性達が忙しく働いている。
秋子が機織り機の前で、正太に話しかけているが、よく聞こえない。
無数の糸ががっしゃんと上下に交差するたびに手前に布が伸びてくるのを、秋子が正太に指差しながら話し続けている。布には模様があって、正太はどうして糸が上下するだけで、こんな模様ができるのか不思議でならなかった。
すのこの上を正太と秋子は、工場の奥へと向かう。
機械と機械の間は狭くはないけれど、女性が働いているので邪魔にならないように歩かなければならない。秋子はなれた足取りでずんずんと先にいく。
入ってきたときと反対側の引き戸を開けると、そこが事務所になっていた。
引き戸を閉めると機織り機の音が静かになる。
「お父さん、正太くんが遊びに来たから工場を見せてあげたの」
お父さんと呼ばれた男の人が椅子から立ち上がった。
見上げるほど背が高く、がっしりとした体格だったが、見つめる眼が秋子にそっくりで、やさしくほほえんでいる。
「いらっしゃい」声もやさしい。
「こんにちは」正太はそう言うのが精一杯だった。
「シュウコと仲良くしてくれているそうで、ありがとう」
秋子のお父さんもシュウコといっている。
「正太くん工場どうだった。すごい音だったでしょう」
感想を求められて正太はどう返事を返していいものか、困ってしまった。
こんな広い工場を見たこともなかったし、びっくりするほど機織り機は並んでいるし、その機織り機から魔法のように布ができてくるし。
「そうか、びっくりしてどういっていいかわからないか」
秋子のお父さんは、正太の気持ちがわかったようにさらに目をやさしく細めて、頷いていた。
正太は機織り機が動くのをもっと見ていたいと思っていたが、30分ほどして母親達のいる和室に戻った。
和室の大きな座卓の上には、菓子をのせた鉢が置かれていた。
「正太さん遠慮無く召し上がれ」
秋子の母親にすすめられて正太は、ちょっと自分の母親をみながら、鉢の中から茶色くて平たい菓子を手にとった。秋子も同じ菓子を手に取る。
「お母さんのこのお菓子なんていうの」
「それは三笠焼き。せっかくだからいただきなさい」
三笠焼は、少年雑誌でみた円盤のような形をしている。上下の円盤のなかにあんこが挟まっていて、香ばしい円盤とあんこをいっしょに噛むと、いままで食べたことのない幸せな味がした。
「おいしい」
一気に食べるのがもったいないくらいの甘さだった。
「正太さん、これからもシュウコと仲良くしてくださいね」
口の中に三笠焼をほおばったまま、正太は大きく首をたてにふった。
こんなおいしいお菓子を食べさせてもらったら、誰の頼みだってことわれないと、正太なりに思っていた。
帰り道、正太はなんで秋子はシュウコというのかと母親にたずねた。
「シュウコちゃんの誕生日は、立秋の日だったので秋の子と書いてシュウコという名前にしたそうよ。でもね、小学校に入ってからシュウコちゃんはシュウコという名前が好きじゃないって、どうしてもアキコじゃなくてはいやだといいだしたんですって」
「立秋ってなあに」
「そうね、今日から秋が始まりますよ、という日のこと」
「ふうん、秋子ちゃんは秋になる日に生まれたということか」
正太は、どうしてシュウコではいけないのか、分からなかった。でも、学校と家とで名前が二つあるというのは、ちょっぴり羨ましかった。
お迎え秋子
初めて秋子の家に行った翌日のことだった。小学校へいく準備をしている正太の耳に、玄関のほうから大きな声が聞こえてきた。
「ショウタくん、学校へ行きましょう」
シ・ヨ・ウ・タ・ク・ンと一言ずつ区切るようにしゃべっている。
「正太、誰かがお迎えにきてるから急ぎなさい」
正太は、大あわてでランドセルを背負い、鉛筆箱をカタカタと鳴らしながら玄関に急いだ。
玄関先の石段の下にいたのは、秋子ともうひとり知らない女の子だった。
それがすべての始まりだった。
その日いらい、雨の日も風の日も、雪の日も日曜日と旗日と夏休み、冬休み以外は、毎朝「シ・ヨ・ウ・タ・ク・ン」の声が玄関先から聞こえるようになった。
「ほら、正太、ガールフレンドがお迎えよ」
小さい方の姉が、秋子の声を聞きつけると正太をからかう。
でも、正太はそんなことは気にしなかった。
秋子が迎えに来てくれるのがたのしみでもあった。
確かに声をかけてくるのは秋子だったが、みんなと連れだって小学校に行くことにかわりはないし、ほんの5分ほどの距離をぺちゃくちゃおしゃべりしながら通うのはたのしい時間だった。
二年生になってもお迎え秋子は毎日玄関先で呼びかけてきたが、3年生になってしばらくして、とつぜん終わりになった。
小学生同士の喧嘩のきっかけはささいなことから始まる。
その時もそうだった、正太は、クラスはちがうが同じ町内の友だちたちと遊んでいたときに、いい争いになった。
争いの原因はベーゴマだった。正太はベーゴマが苦手で、その日も大切にしていたベーゴマをはじき出されて取られてしまった。取り返すために挑戦してはまた取られるで、正太はつい、勝てない相手のベーゴマについて「君のベーゴマはお兄ちゃんが削ったやつだからずるい」といってしまったのだ。
八角形のベーゴマの角を削り鋭くすることで、仲間のベーゴマをはじき出すことができる。正太たちは競って、コンクリートの壁や階段などにベーゴマをこすりつけたりして、角を鋭くした。だが、子どもの力ではそんなに削れない。兄弟のいる友だちは年上の兄に助けてもらったり、時には兄たちのベーゴマを持ってくるときもある。
正太が悔し紛れに思わずいってしまった「ずるい」というひとことで、火がついてしまった。
「なんだ正太なんか、女といっしょに学校へ行ってるじゃないか」
秋子といっしょに小学校へ行っていることが"ずるい"ことといわれて正太は言葉に詰まり、小さな声で「そんなのベーゴマと関係ないじゃないか」と言い返すのがやっとだった。
「ほらみろ、正太は秋子と結婚の約束でもしたのか。いつもおててつないで仲良くっていいな」
いっしょに遊んでいた他の仲間も加勢し始め「シ・ヨ・ウ・タ・ク・ン、いっしょの学校へいきましょ」と、秋子の口まねまでしてくる。
「ボクは、秋子なんか別になんでもないよ」
喧嘩のそっちのけで、正太はむきになって言い返す。
「明日、また秋子がむかえにきたらいっしょに学校いくんだろう」
からかうようにはやしたててくる。
「行かないよ、絶対に行かないよ」と強がっていってしまった翌朝から、正太は誰よりも早く起きて小学校へ行くようになった。
「正太、シュウコちゃんが迎えにきたのになんで先に行ってしまったの」
下校してきたときに母親からいわれたが正太は黙っていた。
その翌朝も、そして次の翌朝も正太は、シュウコが迎えにくる前に家を出た。
正太の母親は、シュウコに「正太は、なんだかシュウコちゃんといっしょに学校へ行くのが恥ずかしいみたいで、ごめんなさいね」と、あやまるのがやっとだった。
秋子は、時間を早めて迎えに来ることもあった。
迎えの声を聞くと、正太はランドセルを背負って、家の裏の崖をよじ登って、山伝いに小学校へ向かったりした。
小学校3年生の夏休みが終わり二学期になると、秋子はのお迎えも終わりになった。
だが、正太と秋子の話はまだまだ続く、続きはまたの機会ということに。
2010年2月22日 13:46